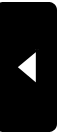本宮山という名前の山は全国各地にありますが、愛知県の本宮山は登山者数の多さが人気の高さを表していて有名です。
麓には「豊川ウォーキングセンター」という施設があり、登山回数などが競うように記録されていて、毎日の日課で頂上近くの「砥鹿(とが)神社奥宮」まで登り続けている人もいます。
ハイキングを始めてまだ間もない2016年の10月に表参道で登った際は、早々にバテてしまい、息も絶えだえで歩いたものです。
体力がなかったのもありますが、あまりに人が多いためにペースがつかめないまま自滅し、どんどん抜かれていって自信喪失しトラウマとなっていました。
山自体はとても素晴らしかったのに、マイペースで歩けない印象が強すぎてずっと避けてきた本宮山。
毎週どこかしらの山を歩き続けて、体力は向上している今、2年ぶりの再チャレンジをしてきました。

豊川市のウォーキングセンター駐車場は、平日でも満車になってしまいます。
早朝6時前に到着しても、既に5~6台の車が停まっていました。
駐車場はここだけでは足りないので、登山口近くの空き地も利用されているほどです。

山の山頂と麓に神社がある例は多く、浜松市春野町の秋葉神社は、麓に下社、頂上に上社がありますが、愛知本宮山の「砥鹿神社」の場合は、麓の豊川市内の街中に「里宮」があり少し離れています。
この砥鹿神社は三河国一宮なのでとても立派な神社です。
私たちの身近な遠江一宮が「小国神社」ですね。
「一宮」というのはその地域の中で最も社格が高いとされる神社を示しています。

登山口から山頂まで、丁石が1から50まであり、順に「鶯(うぐいす)峠」「小栗鼠坂」「野猿坂」とおもしろいネーミングの立札が立っています。
自分も早い時間から登りはじめる方ですが、すぐに下山してくる人と擦れ違い唖然とします。
画像の地点で林道(山頂まで続いているが車両通行止)と一旦出合いますが、ここから一気に急勾配となります。

最初の画像は、岩を削った階段が続く「馬背(うまのせ)岩」付近で、多くの巨石が露出しています。
愛知県の山は、こういった巨石を越えていく印象が強くあります。
「鳳来寺山」「宇連山」「明神山」を思い出させます。



前回はこの展望台で既にグロッキーで大休憩したのですが、今回は止まることなく通過です。
まだ余裕があり、いいペースだと思ったのですが、若い人は追い抜いていきます。
リュック等荷物なしの身軽な装備で歩いている人は常連だと思って間違いないです。
私はどんな山でも何があるかわからない基本を守ってフル装備です。

「猪駆坂」「山姥坂」「風越峠」と順に比較的楽に通過した後、長い階段と鳥居が現れます。


このあとすぐに林道に出て左手に移動、再び山道に入っていく(お清水舎がある)のですが、ここからが本当の体力勝負になります。
距離的には砥鹿神社奥宮まで残りわずかなのですが、険しい階段の連続でなかなか足が前に進まなくなります。
息も切れてペースがガクンと落ちてしまいました。

「荒羽々気(あらはばき)神社」「八柱(やはしら)神社」と続けてあり、いよいよ神社域に入ったことを感じます。
画像はGPSコース図内にあります。
疲れもありますが、人が多いのもシャッターチャンスを減らしていきます。

砥鹿神社奥宮(画像略)の右手に進むと「富士山遥拝所」がありますが、当日は残念ながら真っ白でした。
裏手には「守見殿神社」もあります。
参拝者休憩所の前には「大福釜」が置いてあります。
特筆すべきは100円の自動販売機があることですが、季節柄売り切れが多かったです。
水分は登山前にしっかり用意しておくべきです。

山頂へは鳥居を出て、本宮山スカイラインの上に架かる赤い橋を渡って、もうひと頑張り急坂を登ります。
前回はヘロヘロで凄い時間を費やしたのですが、今回はスムーズに登れました。
多くの方は砥鹿神社で引き返すため、山頂は誰もいずに独占です。


ここから岡崎の「くらがり渓谷」まで行くことができます。






砥鹿神社奥宮、表参道に戻るのに、駐車場から自動車お祓いのための通路を歩くのが一般的ですが、山中を横切る通路があります。
詳細はGPSコース図を見てもらいたいのですが、踏み跡は薄いので自信のない方は避けてください。
一旦下って、再び登り、出口には赤い鳥居があります。
途中に貯水池があり、鯉が泳いでいます。


下山は表参道をそのまま引き返すのが一般的で、私も途中までそうしたのですが、人の多さが嫌になって寄り道していくことにしました。
「ふるさと自然のみち」と書かれた道標の「乙女前神社」案内に従うことにしました。

このすぐ下にもう一つ同じような祠がありました。
そこで下から上がってきた男性がいて、話を聞くとこのまま「牛の滝」へ下山できると言います。
本当は一旦戻って「陽向滝不動尊」を経由して(森林浴と滝めぐりコース)ウォーキングセンターに戻るのが楽だったのですが、「牛の滝」からのルートにも興味がありました。

このルート、蜘蛛の巣だらけだし、足場は荒れ果ててるし、雑草だらけだし、この時期はオススメできません。
ウォーキングセンターの人曰く「誰も歩いていない」コースのようです。
変化があっておもしろい表参道と比べると、人気がないのは仕方ないかもしれません。
山道らしいといえば間違いなく、普通に登れる別ルートとして覚えておいていいでしょう。
「牛の滝」は以前見たことがあったので寄らず、上の画像地点からひたすら車道歩きとなり大変でした。

総距離は13,5km、所要時間は約5時間、歩数計は21,466でした。
数字以上に歩いた感じが残っています。
愛知本宮山表参道は自分の体力と向き合うには絶好だと思います。
一度は歩いてみてください。
麓には「豊川ウォーキングセンター」という施設があり、登山回数などが競うように記録されていて、毎日の日課で頂上近くの「砥鹿(とが)神社奥宮」まで登り続けている人もいます。
ハイキングを始めてまだ間もない2016年の10月に表参道で登った際は、早々にバテてしまい、息も絶えだえで歩いたものです。
体力がなかったのもありますが、あまりに人が多いためにペースがつかめないまま自滅し、どんどん抜かれていって自信喪失しトラウマとなっていました。
山自体はとても素晴らしかったのに、マイペースで歩けない印象が強すぎてずっと避けてきた本宮山。
毎週どこかしらの山を歩き続けて、体力は向上している今、2年ぶりの再チャレンジをしてきました。
険しい山道は体力勝負!
GPSコース図:右上クリックで拡大
豊川市のウォーキングセンター駐車場は、平日でも満車になってしまいます。
早朝6時前に到着しても、既に5~6台の車が停まっていました。
駐車場はここだけでは足りないので、登山口近くの空き地も利用されているほどです。
登山口には砥鹿神社の鳥居
山の山頂と麓に神社がある例は多く、浜松市春野町の秋葉神社は、麓に下社、頂上に上社がありますが、愛知本宮山の「砥鹿神社」の場合は、麓の豊川市内の街中に「里宮」があり少し離れています。
この砥鹿神社は三河国一宮なのでとても立派な神社です。
私たちの身近な遠江一宮が「小国神社」ですね。
「一宮」というのはその地域の中で最も社格が高いとされる神社を示しています。
左が登山道 ここから岩越等一気にハードに
登山口から山頂まで、丁石が1から50まであり、順に「鶯(うぐいす)峠」「小栗鼠坂」「野猿坂」とおもしろいネーミングの立札が立っています。
自分も早い時間から登りはじめる方ですが、すぐに下山してくる人と擦れ違い唖然とします。
画像の地点で林道(山頂まで続いているが車両通行止)と一旦出合いますが、ここから一気に急勾配となります。
ここを登りきると「見返り峠」
最初の画像は、岩を削った階段が続く「馬背(うまのせ)岩」付近で、多くの巨石が露出しています。
愛知県の山は、こういった巨石を越えていく印象が強くあります。
「鳳来寺山」「宇連山」「明神山」を思い出させます。
「梯子(はしご)岩」をよじ登る
こちらは「蛙岩」
蛙岩の反対側には展望台:画像クリックで展望画像
前回はこの展望台で既にグロッキーで大休憩したのですが、今回は止まることなく通過です。
まだ余裕があり、いいペースだと思ったのですが、若い人は追い抜いていきます。
リュック等荷物なしの身軽な装備で歩いている人は常連だと思って間違いないです。
私はどんな山でも何があるかわからない基本を守ってフル装備です。
弘法大師の日月の彫刻がある「日月岩」
「猪駆坂」「山姥坂」「風越峠」と順に比較的楽に通過した後、長い階段と鳥居が現れます。
鳥居の左横には水場がある
「山姥の足跡」と自分の足比べ:画像クリックで説明書き
このあとすぐに林道に出て左手に移動、再び山道に入っていく(お清水舎がある)のですが、ここからが本当の体力勝負になります。
距離的には砥鹿神社奥宮まで残りわずかなのですが、険しい階段の連続でなかなか足が前に進まなくなります。
息も切れてペースがガクンと落ちてしまいました。
2つの鳥居を抜けると「天の磐座(いわくら)」
「荒羽々気(あらはばき)神社」「八柱(やはしら)神社」と続けてあり、いよいよ神社域に入ったことを感じます。
画像はGPSコース図内にあります。
疲れもありますが、人が多いのもシャッターチャンスを減らしていきます。
砥鹿神社はもうすぐそこ
砥鹿神社奥宮(画像略)の右手に進むと「富士山遥拝所」がありますが、当日は残念ながら真っ白でした。
裏手には「守見殿神社」もあります。
参拝者休憩所の前には「大福釜」が置いてあります。
特筆すべきは100円の自動販売機があることですが、季節柄売り切れが多かったです。
水分は登山前にしっかり用意しておくべきです。
さらに山頂を目指します
山頂へは鳥居を出て、本宮山スカイラインの上に架かる赤い橋を渡って、もうひと頑張り急坂を登ります。
前回はヘロヘロで凄い時間を費やしたのですが、今回はスムーズに登れました。
多くの方は砥鹿神社で引き返すため、山頂は誰もいずに独占です。
山頂三角点(789m) 天候が良ければ開放的な展望も楽しめる
山頂から反対側に下って「奥の院・岩戸神社」へ:画像クリックで案内板
ここから岡崎の「くらがり渓谷」まで行くことができます。
「国見岩」左側に男道、右側に女道があり、岩下に岩戸神社
「女道」といってもかなり厳しい下り
岩戸神社に到着
岩の中に神社があります
この岩壁(私の頭上)を登るのが「男道」・・・無理です
戻るのも大変です
砥鹿神社奥宮、表参道に戻るのに、駐車場から自動車お祓いのための通路を歩くのが一般的ですが、山中を横切る通路があります。
詳細はGPSコース図を見てもらいたいのですが、踏み跡は薄いので自信のない方は避けてください。
一旦下って、再び登り、出口には赤い鳥居があります。
途中に貯水池があり、鯉が泳いでいます。
岩戸神社参道出入り口 山頂より先に岩戸神社の方がわかりやすいかも
意外な場所での鯉に癒されました
下山は表参道をそのまま引き返すのが一般的で、私も途中までそうしたのですが、人の多さが嫌になって寄り道していくことにしました。
「ふるさと自然のみち」と書かれた道標の「乙女前神社」案内に従うことにしました。
神社といっても祠があるだけでした
このすぐ下にもう一つ同じような祠がありました。
そこで下から上がってきた男性がいて、話を聞くとこのまま「牛の滝」へ下山できると言います。
本当は一旦戻って「陽向滝不動尊」を経由して(森林浴と滝めぐりコース)ウォーキングセンターに戻るのが楽だったのですが、「牛の滝」からのルートにも興味がありました。
新東名の東上トンネル東側下に出た 登山口はこの右手 駐車も可
このルート、蜘蛛の巣だらけだし、足場は荒れ果ててるし、雑草だらけだし、この時期はオススメできません。
ウォーキングセンターの人曰く「誰も歩いていない」コースのようです。
変化があっておもしろい表参道と比べると、人気がないのは仕方ないかもしれません。
山道らしいといえば間違いなく、普通に登れる別ルートとして覚えておいていいでしょう。
「牛の滝」は以前見たことがあったので寄らず、上の画像地点からひたすら車道歩きとなり大変でした。
牛の滝 以前行ったときの撮影
総距離は13,5km、所要時間は約5時間、歩数計は21,466でした。
数字以上に歩いた感じが残っています。
愛知本宮山表参道は自分の体力と向き合うには絶好だと思います。
一度は歩いてみてください。