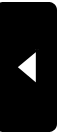先週に続いて遠州森町の最奥地にあたる大日山へ探索も兼ねて歩きに行ってきました。
思いがけずに見つけた尾根ルートを確認したいのと、2019年4月以来となる金剛院を見たかったからです。

スタート地点も一週間前と同じかわせみ湖の彩り岬駐車場でしたが、いきなりハイドレーションの不具合で水漏れがあり、リュックのパッキングを直してロスタイムしてしまいました。
大日山山頂を越えて金剛院まで行って折り返すので、杉沢の大滝はガードレール付の橋上から見るだけで通過しました。
画像は先週の記事で見ることができます。


尾根に上がるまで山の急斜面の道を登りますが、一度下っているだけに様子はわかっているのでゆっくり味わいながら歩きました。
先週新しく見つけた尾根道は、下山するときにスキーのジャンプ台を下るようなイメージがありましたが、実際に登ってみると、最初にも急斜面があって中間は多少のアップダウンも含めて緩やか、最後に山頂まで激しい急登でルートもなくなるというものでした。








順調に登っていたのですが、暑かったので外してポケットに入れておいた手袋を落としたことに気づきました。
これはいけないと引き返して探すのですが、結構な距離を往復することになり、またしてもロスタイムしてしまいました。
急登のない部分だったので体力的にはダメージもなく、負け惜しみを言えば、お気に入りの尾根道なので気持ちよくて苦にならなかったです。
山行タイムなど気にせず、ハプニングも楽しむことが自分のポリシーです。



途中に隣の尾根道と繋ぐルートの分岐点も確認したので、いずれその道も歩いてみます。
正にスキーのジャンプ台の上の方のごとくで、急登はどんどん厳しくなってきました。


上画像の場所で赤リボンが最後になり(まだルートがあるように見えますが)、踏み跡さえも不明瞭の急斜面になります。
先週この場所に辿り着いたのはラッキーだったともいえますが、今回の山行で地形状況がわかったので今後はスムーズに通過できると思います。
大日山の山頂付近が平坦になっていて、どの方面を見ても同じように見えるので地形の把握が難しくさせるのだと思います。
現地でリアルタイムでGPSを使用せずに攻略していくのも山行の醍醐味で、この大日山では存分に味わうことができます。

大日山山頂から金剛院へ下りる東尾根ルートは、森町歩こう会の道標と整備のおかげでとても歩きやすくなっています。
金剛院への下山道ルートを歩いたのは、実に初めての大日山登山の2017年1月以来でした。


遠江の山々にはそれぞれ天狗が祀られていますが、大日山には「繁昌坊」がいて立派な祠が建てられています。





建築や設計のことは全くわからない自分が見ても、いい造りをしていることがわかります。
門内の左右に大きな仁王像が睨みを利かしているのも迫力満点です。
ここで折り返して再び大日山山頂に到達したときは疲労困憊になり、休憩と栄養補給しました。
下山時は山頂部から登ってきた尾根道への入り方を再度確認しました。


山での遭難のほとんどは下山時に起きるというのがよくわかります。
ここより右手(西側)は深い谷底が見えるほど切り立った場所もあるので、下りていく方角の見定めが重要になります。
慎重に下っていくと、登山時に最後に確認した赤リボンの場所に繋がりました。
その急斜面の途中で、少しだけ見晴らしの効く場所がありました。

はっきりと踏み跡がわかる尾根道ルートに入ると一安心でしたが、よくこんな急な道を登ったものだと感心してしまいました。
同じ道でも登るときと下るときはイメージが違うのが不思議ですが、このルートは屈指のお気に入りになりました。

まだまだ探索しきれていない大日山ですが、入山する季節も限られていて(個人判断)、入念な予習復習が必要な山です。
それだけに安全第一を忘れずに挑んでいきたいと思います。

思いがけずに見つけた尾根ルートを確認したいのと、2019年4月以来となる金剛院を見たかったからです。
かわせみ湖から大日山金剛院を往復
GPSコース図
スタート地点も一週間前と同じかわせみ湖の彩り岬駐車場でしたが、いきなりハイドレーションの不具合で水漏れがあり、リュックのパッキングを直してロスタイムしてしまいました。
大日山山頂を越えて金剛院まで行って折り返すので、杉沢の大滝はガードレール付の橋上から見るだけで通過しました。
画像は先週の記事で見ることができます。
2022/01/21
登山口からいきなりの急登
尾根に上がるまで山の急斜面の道を登りますが、一度下っているだけに様子はわかっているのでゆっくり味わいながら歩きました。
先週新しく見つけた尾根道は、下山するときにスキーのジャンプ台を下るようなイメージがありましたが、実際に登ってみると、最初にも急斜面があって中間は多少のアップダウンも含めて緩やか、最後に山頂まで激しい急登でルートもなくなるというものでした。
尾根道に入って山頂へ向かう
倒木も多い尾根道
真っすぐな尾根道が気持ち良い
左右切り立ったところは注意も必要
滑落しないよう足元を注意して登る
順調に登っていたのですが、暑かったので外してポケットに入れておいた手袋を落としたことに気づきました。
これはいけないと引き返して探すのですが、結構な距離を往復することになり、またしてもロスタイムしてしまいました。
急登のない部分だったので体力的にはダメージもなく、負け惜しみを言えば、お気に入りの尾根道なので気持ちよくて苦にならなかったです。
山行タイムなど気にせず、ハプニングも楽しむことが自分のポリシーです。
手袋発見 倒木をくぐったときに落としたようだ
お待たせポール 待機させておいたので不安げだった
気を取り直して再スタート ここからが激急登
途中に隣の尾根道と繋ぐルートの分岐点も確認したので、いずれその道も歩いてみます。
正にスキーのジャンプ台の上の方のごとくで、急登はどんどん厳しくなってきました。
急登もルートがあるだけまだ助かる
ルートもここで終わる
上画像の場所で赤リボンが最後になり(まだルートがあるように見えますが)、踏み跡さえも不明瞭の急斜面になります。
先週この場所に辿り着いたのはラッキーだったともいえますが、今回の山行で地形状況がわかったので今後はスムーズに通過できると思います。
大日山の山頂付近が平坦になっていて、どの方面を見ても同じように見えるので地形の把握が難しくさせるのだと思います。
現地でリアルタイムでGPSを使用せずに攻略していくのも山行の醍醐味で、この大日山では存分に味わうことができます。
山頂到達の喜びは大きい
大日山山頂から金剛院へ下りる東尾根ルートは、森町歩こう会の道標と整備のおかげでとても歩きやすくなっています。
金剛院への下山道ルートを歩いたのは、実に初めての大日山登山の2017年1月以来でした。
2017/01/19
東海自然歩道の登山口にも新しい道標が設置された
久しぶりの金剛院
遠江の山々にはそれぞれ天狗が祀られていますが、大日山には「繁昌坊」がいて立派な祠が建てられています。
2020/07/10
鐘楼の横に祀られている
昔の校舎を思わせる
迫力ある竜がいる手水舎
参道脇(画像左下)に三角点(661.3m) 画像は山門側から金剛院方向
画像クリックで説明書き
建築や設計のことは全くわからない自分が見ても、いい造りをしていることがわかります。
門内の左右に大きな仁王像が睨みを利かしているのも迫力満点です。
ここで折り返して再び大日山山頂に到達したときは疲労困憊になり、休憩と栄養補給しました。
下山時は山頂部から登ってきた尾根道への入り方を再度確認しました。
山頂付近樹木の間から水平線と船のシルエットも見えた
赤リボンを発見してこの急斜面を下る
山での遭難のほとんどは下山時に起きるというのがよくわかります。
ここより右手(西側)は深い谷底が見えるほど切り立った場所もあるので、下りていく方角の見定めが重要になります。
慎重に下っていくと、登山時に最後に確認した赤リボンの場所に繋がりました。
その急斜面の途中で、少しだけ見晴らしの効く場所がありました。
太田川の河口付近だろうか
はっきりと踏み跡がわかる尾根道ルートに入ると一安心でしたが、よくこんな急な道を登ったものだと感心してしまいました。
同じ道でも登るときと下るときはイメージが違うのが不思議ですが、このルートは屈指のお気に入りになりました。
登ってきた山を振り返るのは感慨深い
まだまだ探索しきれていない大日山ですが、入山する季節も限られていて(個人判断)、入念な予習復習が必要な山です。
それだけに安全第一を忘れずに挑んでいきたいと思います。
起点のかわせみ湖に戻った
2020/03/13
2019/02/02
2017/11/24