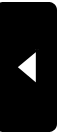島田市の「千葉山(ちばさん)」は、「智満寺(ちまんじ)」という比叡山延暦寺を総本山とする天台宗のお寺があることで知られ、多くのハイキングコースがあり地元の方に親しまれています。
なかでも「尾川丁仏参道(おがわちょうぶつさんどう)」は、島田市のばらの丘公園・中央公園の北側の尾川地区から智満寺までの旧参道で、1丁(約100m)ごとに丁石と石仏が33体並ぶメインコースです。

千葉山山頂(496m)には国の天然記念物である「智満寺の十本杉」が立ち並んでいます。
十本のうち三本は倒木ですが、いずれも800年~1,200を経たもので、残っているものはそれはそれは見事です。
紅葉の季節には県下有数のドウダンツツジの群生地「どうだん原」が有名で、麓にある温泉施設「田代の郷温泉・伊太和里(いたわり)の湯」はとても人気があります。

尾川丁仏参道の33体の石仏、智満寺の十本杉は全て写真撮影してきましたが、数が多過ぎて全ては紹介しきれないのが残念です。
当日は車を「伊太和里の湯」駐車場に停めさせてもらい、車道を40分歩いて尾川丁仏参道入口まで移動して入り、智満寺からは伊太丁仏参道を下って駐車場に戻るという周回コースをとりました。
それぞれの参道を往復するのが一般的ですが、欲張って二つの参道を一気に歩くことができるコース設定です。


参道ハイキングコースはよく整備され歩きやすいもので、ハードな所もなく、丁石と石仏を眺めながら楽しい時を過ごせました。


丁石が並ぶ山は、私が毎月登る秋葉山にもありますし、石仏が並ぶ道は遠州森町の「歴史の散歩道」にもあります。
しかし、長い距離の区間に丁石と石仏のセットでしっかりと手入れされて残っていることが素晴らしいです。
何よりその数の多さは次々と現れるので飽きさせません。

二十町からは舗装された道(車のすれ違い困難な狭さ)になり、下っていきます。
その道の変わりように不安になりましたが、道端には丁石と石仏が引き続きあるので、間違ってないことがわかって安心できます。
長い下り坂の途中には「縁結びの杉」というものもありました。


画像の「亀石」のある箇所で再び車道と合流し、智満寺まではずっと舗装路歩きになります。
この車道は以前、車で智満寺に行ったときに走行したことがあるのですが、とても狭いので神経を使います。
運転が苦手な人には厳しい道です。


滝の周辺には可愛い花が咲いていました。
この滝は修行で使われたのでしょうか?暑い日には滝にうたれたくなりそうです。
滝の横には三十三町目の丁石と石仏があります。

階段の右下には三十四町の丁石が立っていますが石仏はありません。
石垣の上に地蔵菩薩と魚籃観音があり、その横に石仏が一体あるので、それが本来セットのものかもしれません。



智満寺に訪れるのは3度目なのですが、それまで長い階段を登るのにとても大変でした。
ところが今回はあっさり登りきることができて、自分の体力が山歩きの習慣のおかげでアップしていることを実感できました。
また、今までよりもお寺の本堂が大きく感じられたのが不思議でした。
画像クリックで現れたものの中に、実は私が隠れています。
といってもセルフ撮影に失敗したのですが、見つけられるでしょうか?
私の姿と比べてもらうと、智満寺の立派さが浮き立つと思います。

このあと、千葉山山頂を目指して山道を更に登っていきます。
そして「智満寺の十本杉」を巡りますが、それは次回に回させていただきます。
大量の写真を撮影したということは、それだけ見どころも満載だったということで、素晴らしいハイキングコースでした。
なかでも「尾川丁仏参道(おがわちょうぶつさんどう)」は、島田市のばらの丘公園・中央公園の北側の尾川地区から智満寺までの旧参道で、1丁(約100m)ごとに丁石と石仏が33体並ぶメインコースです。
十四町目の丁石と石仏
千葉山山頂(496m)には国の天然記念物である「智満寺の十本杉」が立ち並んでいます。
十本のうち三本は倒木ですが、いずれも800年~1,200を経たもので、残っているものはそれはそれは見事です。
紅葉の季節には県下有数のドウダンツツジの群生地「どうだん原」が有名で、麓にある温泉施設「田代の郷温泉・伊太和里(いたわり)の湯」はとても人気があります。
GPSコース図:右上クリックで拡大
尾川丁仏参道案内図:画像クリックで拡大
尾川丁仏参道の33体の石仏、智満寺の十本杉は全て写真撮影してきましたが、数が多過ぎて全ては紹介しきれないのが残念です。
当日は車を「伊太和里の湯」駐車場に停めさせてもらい、車道を40分歩いて尾川丁仏参道入口まで移動して入り、智満寺からは伊太丁仏参道を下って駐車場に戻るという周回コースをとりました。
それぞれの参道を往復するのが一般的ですが、欲張って二つの参道を一気に歩くことができるコース設定です。
2つの画像は同ポイントから向きを変えて撮影
参道ハイキングコースはよく整備され歩きやすいもので、ハードな所もなく、丁石と石仏を眺めながら楽しい時を過ごせました。
それぞれ違う顔、違う形の石仏を見ていく:十五町
十九町を通過
丁石が並ぶ山は、私が毎月登る秋葉山にもありますし、石仏が並ぶ道は遠州森町の「歴史の散歩道」にもあります。
しかし、長い距離の区間に丁石と石仏のセットでしっかりと手入れされて残っていることが素晴らしいです。
何よりその数の多さは次々と現れるので飽きさせません。
2017/02/02
2017/06/01
2017/07/09
二十町はしっかりと小屋の中に
二十町からは舗装された道(車のすれ違い困難な狭さ)になり、下っていきます。
その道の変わりように不安になりましたが、道端には丁石と石仏が引き続きあるので、間違ってないことがわかって安心できます。
長い下り坂の途中には「縁結びの杉」というものもありました。
石垣の上の山道に入り下っていく車道と分かれる
「亀石」に触れる・二十七町:画像クリックで説明分
画像の「亀石」のある箇所で再び車道と合流し、智満寺まではずっと舗装路歩きになります。
この車道は以前、車で智満寺に行ったときに走行したことがあるのですが、とても狭いので神経を使います。
運転が苦手な人には厳しい道です。
智満寺入口に到着 きつい階段登りが待っている
入口横の「霊水の滝」を見る:画像クリックで別角度
滝の周辺には可愛い花が咲いていました。
この滝は修行で使われたのでしょうか?暑い日には滝にうたれたくなりそうです。
滝の横には三十三町目の丁石と石仏があります。
この階段を見てください!
階段の右下には三十四町の丁石が立っていますが石仏はありません。
石垣の上に地蔵菩薩と魚籃観音があり、その横に石仏が一体あるので、それが本来セットのものかもしれません。
仁王門 その先にも階段が待ってます
中門まで最後のがんばりどころ
からぶき屋根が特徴的な智満寺:画像クリックで別角度
智満寺に訪れるのは3度目なのですが、それまで長い階段を登るのにとても大変でした。
ところが今回はあっさり登りきることができて、自分の体力が山歩きの習慣のおかげでアップしていることを実感できました。
また、今までよりもお寺の本堂が大きく感じられたのが不思議でした。
画像クリックで現れたものの中に、実は私が隠れています。
といってもセルフ撮影に失敗したのですが、見つけられるでしょうか?
私の姿と比べてもらうと、智満寺の立派さが浮き立つと思います。
手水舎には金魚が泳ぐ
このあと、千葉山山頂を目指して山道を更に登っていきます。
そして「智満寺の十本杉」を巡りますが、それは次回に回させていただきます。
大量の写真を撮影したということは、それだけ見どころも満載だったということで、素晴らしいハイキングコースでした。