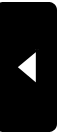愛知県奥三河の「宇連山(うれやま)」は、「愛知県民の森」という広大な公園内に東西南北の名の付いた尾根を持ち、滝や岩稜の大自然を味わいながら、よく整備されたハイキングコースで向かうことができるお山です。
愛知県民の森から宇連山は、今まで2度別コースで歩いていますが、最も距離が遠くなる「東尾根」はまだ経験がなく、自分の脚力がどれだけ通用するか、いつか挑戦してみたいと思っていました。
当日はとにかく東尾根から宇連山山頂へと、それだけを計画して出発しました。

今回GPSがうまく作動せず、行程が記録されていなかったのが非常に悔やまれるのですが、上の地図で緑色部分が愛知県民の森の敷地(名古屋ドーム約120個分の広さ)で、その外枠を反時計回りで周回(宇連山山頂含)したのが当日のコースです。
愛知県民の森のゲートが開くのが朝7時(実際は10分程早かった)で、駐車場に1番乗りしてすぐにスタートしました。
宿泊施設の「モリトピア」から右手(東)へ進み、川を橋で渡ると「Aキャンプ場」に入ります。
そこに登山口があり、「シャクナゲ尾根」から「東尾根」を目指します。


長い車道や林道を移動して登山口に辿り着くパターンもある中、すぐに山道に入れて歩けるのはハイカーには非常に嬉しく高ポイントです。
「南尾根」も、逆方向の「Bキャンプ場」に入るとすぐに登山口があります。
「北尾根」から入ったときは、施設中央にある林道をかなりの距離移動してからでした。



「南尾根」が解放感抜群の岩尾根なのと対照的に、「シャクナゲ尾根」は森の中の岩尾根といった感じでした。
「シャクナゲ尾根」「シャクナゲ北尾根」と順に合流して「東尾根」に入りますが、道中展望が開ける場所からは最高の景色を楽しめました。













道標はありませんが、この地点から東へ進むと「上臈(じょうろう)岩」に行かれて、その迫力ある眺望から最近人気があり、山頂を目指さず上臈岩を目的に歩く人が増えているようです。
この地点でスタートしてから2時間でした。

下っていくと「シュートン沢」からのルートが合流してきて、そこからは昨年の12月に歩いています。
前回は林道を歩いてきた部分を、今回はずっと山を越えて歩いてきているわけです。









「北尾根」と「西尾根」の分岐点から宇連山まではピストン(片道約1㎞)となります。
この往復は当たり前ですが今までで一番きつかったです。
既に下ってくる単独男性2人とすれ違いましたが、自分が一番遠回りして山頂に来ていることを実感しました。
山頂ではご夫婦が昼食をされていたので、トップ画像の撮影をしただけですぐに下山を始めました。(11時40分)

「西尾根」で下山するのは3度目ですが、前はそれぞれ途中の「滝尾根」「国体コース尾根」で下石林道へ下りています。
どちらも急な下りで大変だった覚えがあり、アップダウンはあっても緩やかに下っていく方が足にやさしいかもという考えで、「南尾根」まで行ってしまうことにしました。
「南尾根」まで行けば県民の森の尾根を全周することにもなります。
健脚の人でないとできないことだと思っていたことに、挑戦してみたくなりました。

道標には登山口のある「Bキャンプ場」まで2時間とあります。
この時点で午後1時5分、疲れでペースが上がらないけど3時半頃には下山できるだろうと予想しました。




「南尾根」に入ると、疲労感から踏ん張れなくなり足元が安定しなくなりました。
昨年の4月以来なので正直記憶も薄れていて、こんなに激しい道だったのかと思いました。
アップダウンも激しいのですが、一方的に下ると足先が痛くなるけど、登り時はきついけど足先は楽という状況でした。
岩の登山道は登り時は踏ん張りが効いて楽ですが、下り時は足の負荷が半端なく強く大変です。
靴底がめくれあがってしまったかのような錯覚をした程です。
下手に転倒すればケガもするし、滑落の危険もあります。
セルフ撮影する余裕は全くありませんでした。







最後の下りは足を真っすぐ着けないほど足先が痛くなっていました。
キャンプ場ではすぐに水場に行って、頭から水をかぶりました。
こういうことができるのはありがたいことです。
トイレをモリトピアで借りて、駐車場の車に戻ったのは午後2時50分でした。
約20㎞、約8時間、歩数計は29,464(活動量計は30,489)、数字的には新記録ではないものの、ずっと山中を歩いた記録としては断トツです。


一週間前は道なき道、藪道をルート探しする山行でしたが、愛知県民の森はルートが明瞭でひたすら歩くという対照的な山行を楽しませてもらいました。
全尾根周回は、逆回りも含めてまた歩いてみたいです。
あと「東尾根」に繋がる「中尾根」ルートが残っています。
鳳来寺山と2座まとめての周回もいつかはと思っています。
(※ 2019年11月に逆回りを行いました)
(※ 2020年12月に中尾根を登りました)
宇連山は愛知県民の森から以外でもルートがあり以前歩いていますが、どこから歩いても長距離になり濃い内容で満足させてくれます。
非常に私好みのお山です。
ハイキングに良い季節になってきました。
クモの巣は大分少なくなってきましたが、ヘビは見ました。
相応しい服装で、装備を万全にしてハイキングを楽しんでください。
愛知県民の森から宇連山は、今まで2度別コースで歩いていますが、最も距離が遠くなる「東尾根」はまだ経験がなく、自分の脚力がどれだけ通用するか、いつか挑戦してみたいと思っていました。
当日はとにかく東尾根から宇連山山頂へと、それだけを計画して出発しました。
2018/04/20
2018/12/28
宇連山山頂(929m)東尾根から4時間半で辿り着いた
宇連山と愛知県民の森
今回GPSがうまく作動せず、行程が記録されていなかったのが非常に悔やまれるのですが、上の地図で緑色部分が愛知県民の森の敷地(名古屋ドーム約120個分の広さ)で、その外枠を反時計回りで周回(宇連山山頂含)したのが当日のコースです。
愛知県民の森のゲートが開くのが朝7時(実際は10分程早かった)で、駐車場に1番乗りしてすぐにスタートしました。
宿泊施設の「モリトピア」から右手(東)へ進み、川を橋で渡ると「Aキャンプ場」に入ります。
そこに登山口があり、「シャクナゲ尾根」から「東尾根」を目指します。
登山口:画像クリックで道標拡大
すぐに山道に入れるのは嬉しい
長い車道や林道を移動して登山口に辿り着くパターンもある中、すぐに山道に入れて歩けるのはハイカーには非常に嬉しく高ポイントです。
「南尾根」も、逆方向の「Bキャンプ場」に入るとすぐに登山口があります。
「北尾根」から入ったときは、施設中央にある林道をかなりの距離移動してからでした。
こんなに天気が良い中を歩くのは久しぶり
岩尾根が始まる これどうやって登る? 岩左下注目
ルートは岩下を巻いていた
「南尾根」が解放感抜群の岩尾根なのと対照的に、「シャクナゲ尾根」は森の中の岩尾根といった感じでした。
「シャクナゲ尾根」「シャクナゲ北尾根」と順に合流して「東尾根」に入りますが、道中展望が開ける場所からは最高の景色を楽しめました。
鳳来寺山
目指す宇連山は遥か遠い
ルートはよく整備され歩きやすい
遠くまで見渡せる季節になりました
北方の眺望 中央特徴的な形状の山は「平山明神山」
こちらは東の眺望「三ツ瀬明神山」 手前に巨岩「上臈岩」見事なツーショット
「東尾根展望台」に到着
見上げる宇連山 まだ遠いなあ~
心落ち着くこんな道が好き
「東尾根」から「北尾根」へ
道標はありませんが、この地点から東へ進むと「上臈(じょうろう)岩」に行かれて、その迫力ある眺望から最近人気があり、山頂を目指さず上臈岩を目的に歩く人が増えているようです。
この地点でスタートしてから2時間でした。
「北尾根」のルートが目視できる その向こうに宇連山
下っていくと「シュートン沢」からのルートが合流してきて、そこからは昨年の12月に歩いています。
前回は林道を歩いてきた部分を、今回はずっと山を越えて歩いてきているわけです。
険しい登りの連続
岩尾根で振り返る(東方面):画像クリックでK280からの南方展望
宇連山に少し近づいたかな?
巨石をすり抜けると・・
「北尾根展望台」展望はあまりよくない
「大幸田峠」道標多過ぎ!
大幸田峠から急峻な登りが続き厳しかった
「北尾根」と「西尾根」の分岐点から宇連山まではピストン(片道約1㎞)となります。
この往復は当たり前ですが今までで一番きつかったです。
既に下ってくる単独男性2人とすれ違いましたが、自分が一番遠回りして山頂に来ていることを実感しました。
山頂ではご夫婦が昼食をされていたので、トップ画像の撮影をしただけですぐに下山を始めました。(11時40分)
山頂からの三ツ瀬明神山
「西尾根」で下山するのは3度目ですが、前はそれぞれ途中の「滝尾根」「国体コース尾根」で下石林道へ下りています。
どちらも急な下りで大変だった覚えがあり、アップダウンはあっても緩やかに下っていく方が足にやさしいかもという考えで、「南尾根」まで行ってしまうことにしました。
「南尾根」まで行けば県民の森の尾根を全周することにもなります。
健脚の人でないとできないことだと思っていたことに、挑戦してみたくなりました。
「国体尾根」分岐 今回は真っすぐ「南尾根」へ進む
道標には登山口のある「Bキャンプ場」まで2時間とあります。
この時点で午後1時5分、疲れでペースが上がらないけど3時半頃には下山できるだろうと予想しました。
緊張感を維持して下山する
三ツ瀬明神山があんなに高く、遠く 下っているのがわかる
西側展望 鳳来寺山は近づいて見える
「南尾根」に入ると、疲労感から踏ん張れなくなり足元が安定しなくなりました。
昨年の4月以来なので正直記憶も薄れていて、こんなに激しい道だったのかと思いました。
アップダウンも激しいのですが、一方的に下ると足先が痛くなるけど、登り時はきついけど足先は楽という状況でした。
岩の登山道は登り時は踏ん張りが効いて楽ですが、下り時は足の負荷が半端なく強く大変です。
靴底がめくれあがってしまったかのような錯覚をした程です。
下手に転倒すればケガもするし、滑落の危険もあります。
セルフ撮影する余裕は全くありませんでした。
果てしなく続く岩の道
振り返って 三ツ瀬明神山があんなに遠くに離れた
「南尾根展望台」あと少しのはず:画像クリックで展望画像
ルートがよくわかる まだまだあるぞ~
ようやくここまで下ってきた 西側展望
Bキャンプ場に到着 完踏した
最後の下りは足を真っすぐ着けないほど足先が痛くなっていました。
キャンプ場ではすぐに水場に行って、頭から水をかぶりました。
こういうことができるのはありがたいことです。
トイレをモリトピアで借りて、駐車場の車に戻ったのは午後2時50分でした。
約20㎞、約8時間、歩数計は29,464(活動量計は30,489)、数字的には新記録ではないものの、ずっと山中を歩いた記録としては断トツです。
一週間前は道なき道、藪道をルート探しする山行でしたが、愛知県民の森はルートが明瞭でひたすら歩くという対照的な山行を楽しませてもらいました。
全尾根周回は、逆回りも含めてまた歩いてみたいです。
あと「東尾根」に繋がる「中尾根」ルートが残っています。
鳳来寺山と2座まとめての周回もいつかはと思っています。
(※ 2019年11月に逆回りを行いました)
2019/11/22
(※ 2020年12月に中尾根を登りました)
2020/12/05
宇連山は愛知県民の森から以外でもルートがあり以前歩いていますが、どこから歩いても長距離になり濃い内容で満足させてくれます。
非常に私好みのお山です。
2019/04/19
ハイキングに良い季節になってきました。
クモの巣は大分少なくなってきましたが、ヘビは見ました。
相応しい服装で、装備を万全にしてハイキングを楽しんでください。